
“誰かのために”は、変わらない。セブン&アイ・ネットメディア 福永さんの働き方
どんな仕事にも必ず「原点」があります。学生時代に友人と過ごした時間や、アルバイト、あるいは、誰かからもらったひと言が「原点」かもしれません。
「働き方は、なないろに」では、セブン&アイグループの従業員一人ひとりの原点から今にいたるまで、それぞれの七色の働き方を紐解いていきます。
今回登場するのは、セブン&アイ・ネットメディア プラットフォーム・サービス部 クラウドエンジニアリングチームの福永さん。
セブン&アイ・ネットメディアは、セブン&アイ・ホールディングスのITシステム会社として、システム企画、デザイン、開発、運用などを通じて、セブン&アイ・ホールディングス関連会社がお客様のさまざまなニーズにお応えするための、サービス実現を支えています。
その中で福永さんは、クラウドエンジニアとして、グループ関連会社のデジタルインフラとしての“土台”をつくっているのです。
そんな福永さんの始まりは、宮崎県の山あいにある静かなお寺で過ごした少年時代にありました。
※このページ内の画像の加工や二次利用を禁止します。
自然と、お寺と、人と
「イノシシやシカ、タヌキが家の庭先に現れる。そんな自然に囲まれた環境だったんですよね。家の周りには本当に何もなくて、学校に行くのも友達のところへ遊びに行くのも、ひたすら自転車をこいでいました」
福永さんが生まれ育ったのは、宮崎県国富町。小高い山に囲まれ、町のあちこちに古墳が点在するなど、豊かな自然と歴史が共存する土地です。福永さんの実家である紫雲山 光西寺(しうんざん こうさいじ)は、山の中腹に建てられたお寺で、1462年の創建以来、地元の人々の心の拠りどころとなってきました。

高校時代まで過ごした福永さんの実家、紫雲山 光西寺。
「お寺ですから、実家の手伝いといえば作務(さむ)※でした。中でも今もよく覚えているのが、大晦日の夜のことです。真冬の寒空の下で除夜の鐘を鳴らすか、暖かいところで正座をしながらお経を一緒に読むか。どちらを担当するかは、兄とジャンケンで決めたり、途中で交代したりしていました」
※掃除や炊事、庭や建物の手入れなどの労働
除夜の鐘を鳴らし終わっても、作務は終わりではありません。今度は、お寺にやってくる地元の方々にお雑煮を振る舞います。福永さんたちがお雑煮を食べられるのは、参拝が一段落してから。
「でも、楽しかったですよ。おかげで除夜の鐘を鳴らすのは上手になりました(笑)」
そんなふうに、お寺の暮らしの中で地元の人たちとも交流しながら育った福永さん。だからなのか、物心ついた時には「大人になったら、誰かの役に立つ仕事をする」と自然に考えるようになっていたといいます。
誰かの役に立ちたい、そのかたちを探して
「最初は医学部に進もうとしていたんですが、途中で血が苦手なことに気づきまして…。それなら、心のケアはどうだろうと考えて臨床心理学に興味を持った時期もありました」

しかし、福永さんが進路先として最終的に選択したのは、社会福祉でした。
「もちろん心のケアも大切ですが、それよりも、日常の暮らしの中で誰かに寄り添う仕事が自分には合っているんじゃないかと思ったんです。大学時代は児童福祉のボランティアにずっと関わっていて、卒業後もしばらく手伝っていました。半分は学業、半分は趣味みたいな感覚でしたね」
大学卒業後は介護施設に就職。児童福祉が好きだったにもかかわらず介護を選んだ理由を、福永さんは「実家の祖父母のためだった」と振り返ります。
「児童福祉も素晴らしい仕事だと思いますが、おじいちゃん・おばあちゃん子だった私にとっては、最終的に介護の方が身近だったんです。介護の仕事に就けば、いつか祖父母の役に立てるだろうって想いがありました」
福永さんは介護施設で4年間勤務し、施設長まで経験。仕事を通して、多様な背景を持つ人々との関わり方を学んでいったといいます。
「あまりきっちりしすぎると、嫌がられるんですよ。むしろ、ちょっとラフなくらいがちょうどいい。毎週、それこそ人によっては毎日会う方もいたので、“これは仕事ですから”ってやり取りをしていると、関係づくりができないんです」
最初は苦労したものの、日々のやり取りを重ねるうちに少しずつ“つながり”を育んでいく。そんな仕事にやりがいを感じる一方で、別れとも向き合うことになる介護の現場に、次第に葛藤も抱えるようになっていきました。
「福祉というかたちではなくてもいいから、誰かの役に立ちたい。そう考えていた時、手元にあったのがスマートフォンでした」
エンジニアという、新しい“支える”かたち
福永さんがIT業界へと転職したのは2016年。スマートフォンの進化が、私たちの暮らしやサービスのかたちを変えようとしていた頃でした。
介護とはまったく違う業界。でも、共通しているのは、人々の暮らしを支えているということ。しかも、IT業界は日々、目に見える速さで変わっていく。そんな業界の在り方に、福永さんはのめり込んでいったそうです。

「最初は情報端末のテストを行うところから始まって、その2年後にはアプリのクラウド移行を担当することになりました。クラウドというのは、たとえばアプリのデータなら特定の端末に保存するのではなく、インターネット上に置くことで、いつでもどこからでもアクセスできるようにする仕組みですね」
5年間の経験を積み、福永さんは2022年12月にセブン&アイ・ネットメディアへ入社。当初は前職と同様にアプリの担当を希望していましたが、「クラウドで、グループ会社のインフラをつくってみたら?」という面接でのやり取りがきっかけで、クラウドエンジニアリングの道を歩むことに。
「面接は和やかな雰囲気で、これまでの経験をもとに『こういう仕事にも挑戦できるのでは?』と言ってもらいました。当初希望していた職種とは少し違いましたが、やってみようと思い、転職にはあまり迷いがありませんでしたね。クラウドがこれからのインフラを変えていくのは確実でしたし、そうやって誘ってもらえたこともうれしかったんです」

現在、福永さんが手がけているのは、グループ内への業務提案やクラウドサービス支援です。
「今の仕事の面白さは、とにかくいろいろな企業のアプリやホームページ、システムに触れることですね。業界を見渡してみても、これだけ幅広く仕事ができる会社はそう多くないと思います。新しい技術の導入もすぐに検討できるので、自分の進化も感じやすいんです」
すっかりエンジニアの顔になった福永さんですが、特に力を入れているのはグループ内の事業会社とのコミュニケーションです。

「エンジニアって専門用語を使いがちなんですが、私たちだけが分かっていても意味がないんですよね。だから、ちゃんと“通じる言葉”で話すことを心がけています。
一方で、事業会社はコンビニエンスストアやスーパーなど業種が違うので、私たちエンジニアとはまた違った視点や、現場ならではの価値観を持たれています。常にその背景や業務の流れを理解しながら、同じ目線で課題に向き合うことも大事ですね」
立場も考え方も違う人々と、関係をつくっていく。
業界はまったく違っても、福永さんが「利用者のために」と介護施設時代に培ったコミュニケーション力は、今の仕事にも息づいているのかもしれません。
最後に、福永さんの働き方を色で表現していただきました。
働き方は、黄色? 緑色?

「普段、自分が何をしているだろうって振り返ってみると、コミュニケーションが好きなんですよね。職場でもそうですし、プライベートでは、友人や東京に出てきている兄妹と過ごす時間を大切にしています。実は、自分では色を決められなかったので、兄夫婦に相談してみたんです。そうしたら、二人とも違う答えで(笑)」
お兄さんから見た福永さんは、“黄色”。
「最初は、子どもの頃の雨合羽が黄色だったから、黄色って言われたんです(笑)。もちろん冗談なんですが、兄なりに私を見ていてくれたんだなと思いました。というのも、黄色にした理由は“笑顔でどんどんコミュニケーションを取るから”だそうなんです。確かに、話すことは好きだなと」
お義姉さんは、福永さんを“緑色”で表現しました。
「穏やかで、人をサポートしているよねって言われました。最近、兄夫婦のところに子どもが生まれたんですね。それで自分がベビーベッドを義姉の実家まで運んでいったので、そういうふうに言ってくれたんだと思います。だから、黄色でもあって、緑色でもある。ライムグリーンが私の色なのかもしれないです」
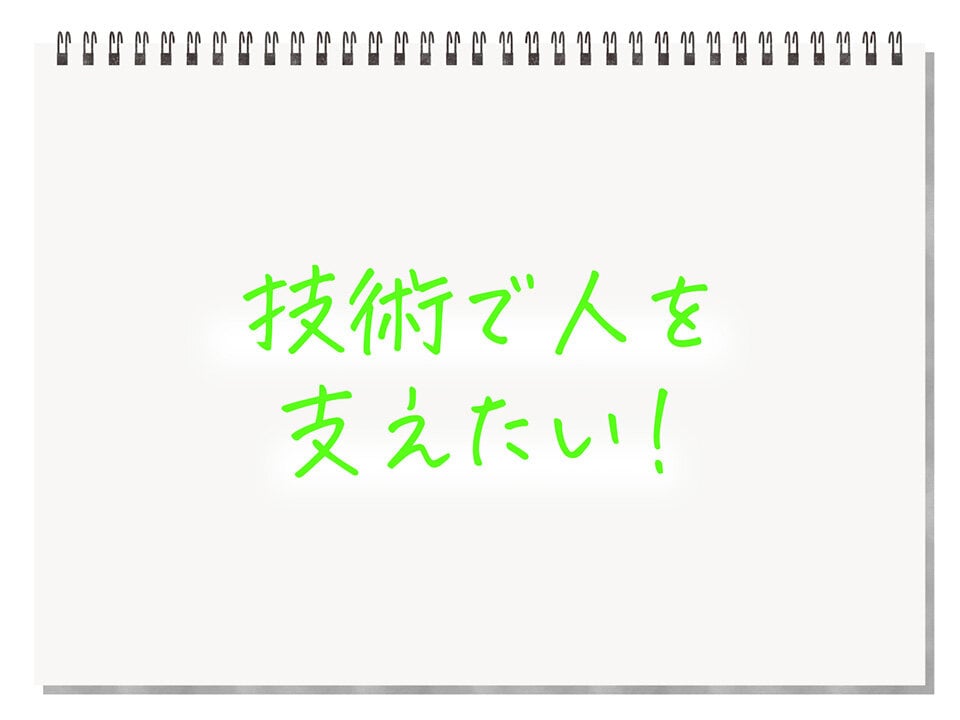
エンジニアの仕事といっても、結局は人と人をつなぐ仕事。宮崎県国富町の山寺で、そして介護の現場で人と触れ合ってきた福永さんは今、子どもの頃に抱いた「誰かの役に立ちたい」という想いをかたちにしています。
福永さんの“ライムグリーン”の物語は、これからも温かに続いていきます。

アンケートフォーム




